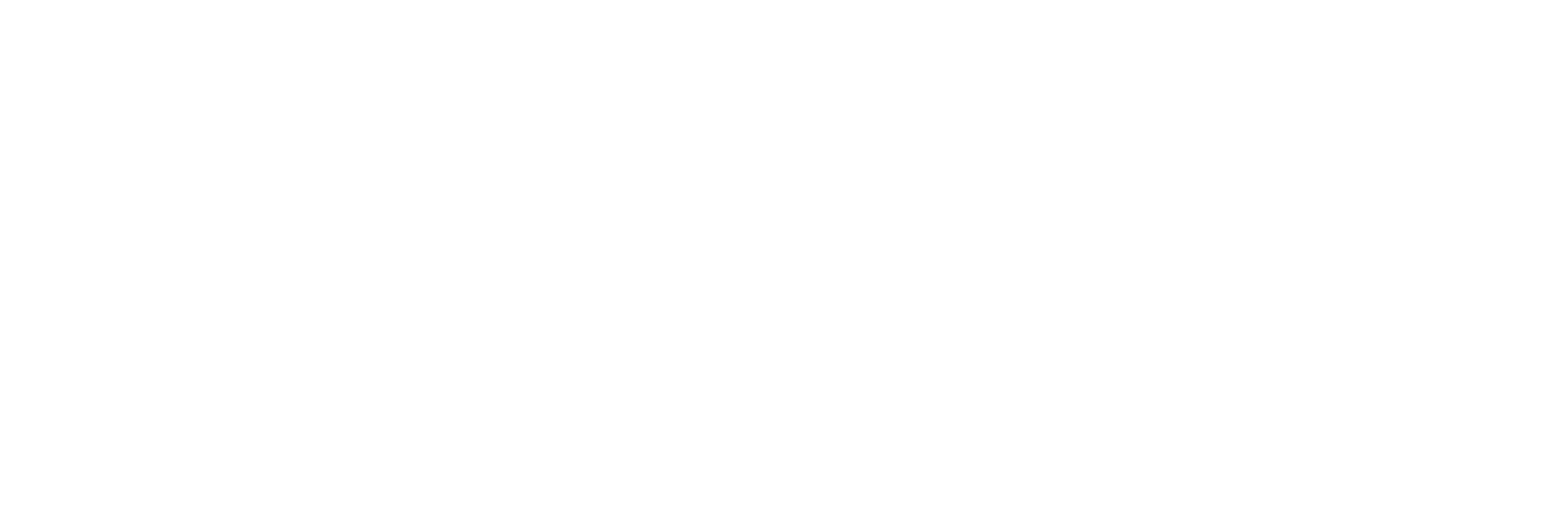本研究は「弱さ」の研究である。弱さとは例えば、脆弱さ、負けてしまうもの、消えやすいもの、私的なこと、不安定さ、曖昧さ、少数派、障害者、性的マイノリティー、中途半端さ、ケアの必要なもの、などが挙げられる。
本論文では、少数派の現場で積み上げられた研究を「弱さ」を考えるうえで、とくに重要な参照点として理論的な要にしている。しかしながら、筆者の「弱さ」への関心は、理論的にというよりも経験的、個人的な経験にはじまっている。
それは祖父のこと、亡くなった祖父にまつわる記憶である。祖父は私が生まれる一年前に交通事故に遭い、下半身不随と脳損傷による知的障害を負った。そしてそれから亡くなるまでの約30年間、ベッドの上で人生を過ごした。祖父の、声にならない声で童謡を歌ったり、タスケテクレ、タスケテクレ、とベッドの上からあげる声、まるで壊れたロボットのように数個のプログラムされた動作を繰り返す様子が今でも脳裏に焼き付いている。祖父は障害を負って以降、基本的には障害者施設で暮らしていた。私が幼い頃は私たち家族で出向くことも多く、施設で開催される催しに参加することもあった。そのなかで最も印象に残っているのは、運動会である。その運動会では施設の入居者や職員、そして親類が合同で参加するのだが、入居者はそれぞれ抱えている障害が異なり、競争を成り立たせる範例的身体が存在せず、能力を順位づける競争は機能しない。それが単に競争原理にもとづかない運動会という意味的な面白さだけではなく、そこに集う人間たちが、目に見えて共約不可能なばらばらで意味をなさない集合であることの空気感自体が居心地のよいものだった。
そのような施設に入居している祖父の里帰りのため、一年に数回迎えに行くのが私たち家族の役目だった。京都北部の故郷(私の父の出身地でもある)は典型的な過疎地域であり、いわゆる田舎である。その数日間祖父の面倒を見るため、父の妹家族が住んでいるかつての実家に祖父の子供達家族が集まり、面倒を見る。それはご飯をたべさせる、服を着替えさせる、オムツを替える、お風呂に入れるなど、何もできない赤ん坊の面倒を見ることとほとんど同じケアをするのだ。赤ん坊は泣き叫ぶことによって自身の不快感を示すが、祖父の場合は暴力を振るう。もともと事故に遭う前はひどい家庭内暴力を振るっていたらしい。しばしば離婚の話が出ていたらしく、事故当日も祖母が耐えきれず離婚を告げたところ、原付で家を飛び出しトラックにはねられたと私の叔母(父の妹)は言っていた。だから、このような履歴を持つ祖父のケアをすることは、その子供たちや、妻である私の祖母にとってはある意味で調和的なケアとは程遠い、葛藤や軋轢を抱えた心境があったように思う。たんにこうした履歴をもつだけではなく、実際のケアの場面においても、暴力は日常的に生じていた。幼い子供であった私もケアを手伝っている最中に殴られることがしばしばあった。私自身が経験したものはケアの一部であったものの、いわゆるケアとして想定される保護されるべき弱者を隅々までサポートするようなものではない。そしてまた基本的には施設で面倒をみてもらっていたので十全なケアとはいえないだろう。部分的なケアでしかないケア。だとしたらこのような「ケア未満」のケアをケアの具体的事例として語ることはできるのだろうか。語ることができる、と私は考える。そしてこのような「ケア未満」のケアについて個別具体的な語りが生まれていくことが、当事者問題として語られ他人事として理解されがちなケアを、アクセスすることがややもすると閉ざされがちな事態を、私たちの問題として共有するために必要な行為であると考えている。つまりケアはけっして当事者問題として処理されがちな「私的」な問題ではなく、きわめて「公的」であるがゆえに「政治的」な概念である。
第1部では、そうした「私的」な問題として他者がアクセスする経路が閉ざされてしまいがちな「弱さ」をすくい上げアクセス可能にするための方法論について考えたい。前半部(1章)では、少数派の現場で語られる議論・研究について参照し、弱さが可視化される試みがいかにしてなされているのかを見ていきたい。参照するのは、フェミニズムの公私二元論批判、当事者研究の「問う」営み、そしてゲイ・スタディーズの境界事例である。これら少数派の現場から生み出される理論から、本研究において着目する「弱さ」が通俗的な「弱さ」のイメージとは別種のものであることを明確にし、技法としての「弱さ」を考えてみたい。後半部(2章)では、組織構造の逆機能というべき問題が、少数派の現場にとどまらず、社会システムのレベルでも見出されることに注目したい。本論文では現代社会のあらゆるところに見出される官僚的組織構造を持つものの中で、自身の表現手段とかかわるメディア環境の問題に焦点を当てる。環境管理型権力およびフィルター・バブルにおける問題、つまり「囲まれた世界」から抜け出す方法について考える。前半部で注目した「弱い技法」を境界性、無目的、遊びという概念と結びつけ、「囲まれた世界」からの抜け穴として解釈し、第2部の議論に接続する。
第2部では、前半部(1章、2章、3章)で自身の作品を含む境界的で虚構的な作品事例をとりあげる。これらは虚構を用いて対抗的な現実をつくることを志向している。境界的であるというのは、安直にボーダレス世界を夢見るのではなく、差別(非対称な分割線)などないという言説へ対抗的な視点を有するということである。虚構的というのは、少数派の現場で生まれる技法を別の角度から見たときの「弱い技法」である。後半部(4章)では、これら境界的で虚構的な特徴を有する対抗的な現実の実践に連なるものとして、自作のロボットのデモ行進《Dæmonstration》について説明する。
第3部では、《Dæmonstration》がライブであり、展示空間での鑑賞という形式に落とし込もうとした時の問題、つまり鑑賞モデルの限界を乗り越えるために、制作した《DEMO DEPO》について説明する。《DEMO DEPO》はお店とワークショップという二つの形式から成っており、それぞれの形式の特性と発生した状況について考察する。
私たちの社会における「弱さ」と呼ばれるものに着目し(第1部)、それら弱い対象を既存の問題設定を揺るがす「問いの誘発装置」としてメディア表現の立場から再解釈し(第2部)、「弱い技法」の可能性を探求する(第3部)。